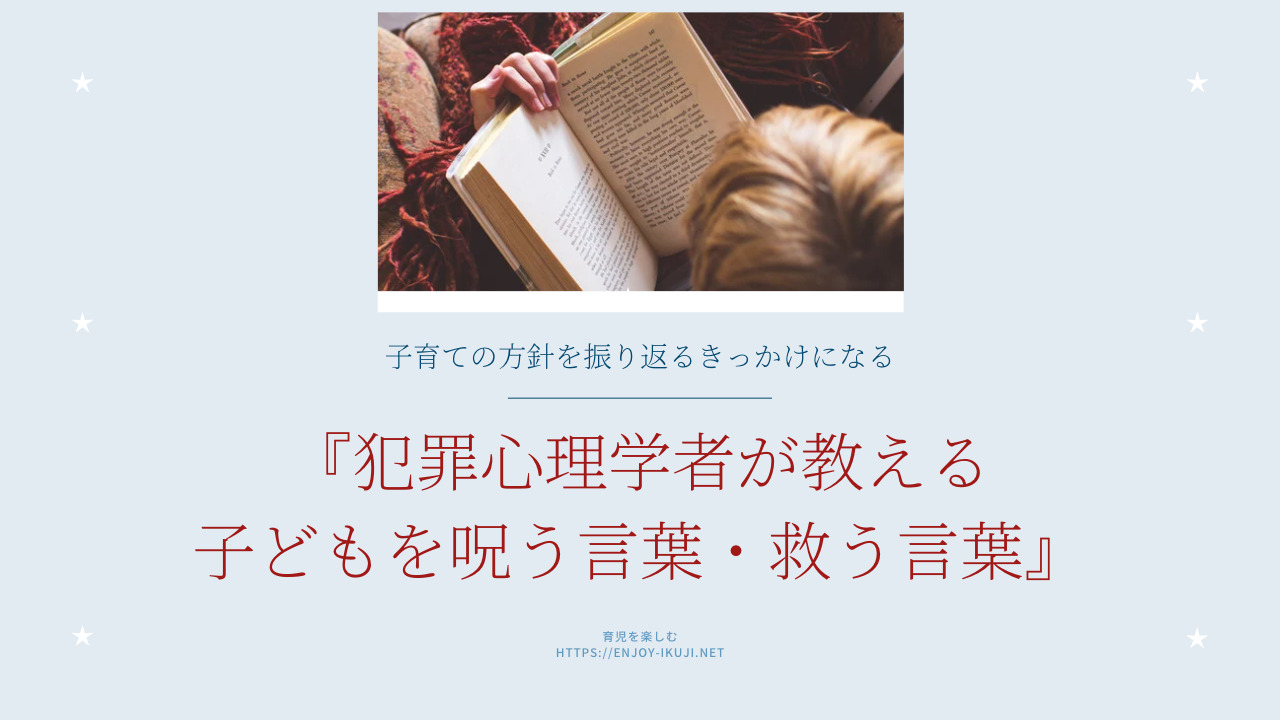子育ての方針が合っているか、子どもに話しかけている言葉が本当に子どものためになっているか悩んだことはありませんか。
子育てに正解はないと思います。
しかし、出口保行(2022)『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』SBクリエイティブ株式会社(以下、『子どもを呪う言葉・救う言葉』とします)を読むと、子育ての方針を振り返るきっかけになり、悩みが軽くなるかもしれません。

こんにちは。ダイチです。
私は、2人の子ども(2歳差)の父親で、育児と仕事の両立を目指しています。
育児に役立つ情報を共有したいと思い、ブログを作っています。
『子どもを呪う言葉・救う言葉』の表紙を見た時、私が子どもよく言っていた言葉「早くしなさい」が「危ない一言」となっていて本書を読むことにしました。
『子どもを呪う言葉・救う言葉』を読めば、子どもに言ってはいけない「危ない一言」を知ることができ、幼児期以降の子育てで大きく失敗することを減らすことができると思います。
子どもに「危ない一言」を使っていないか
「危ない一言」とは
『子どもを呪う言葉・救う言葉』での「危ない一言」とは、子どもを犯罪に走らせることになった言葉です。
犯罪心理学者である『子どもを呪う言葉・救う言葉』の著者・出口保行氏が自身の1万人を超える犯罪者・非行少年の心理分析を行った経験から、事実をもとにした事例によって以下の6つの「危ない一言」を紹介しています。
- 「みんなと仲良く」
- 「早くしなさい」
- 「頑張りなさい」
- 「何度言ったらわかるの」
- 「勉強しなさい」
- 「気をつけて!」
子育ての方針を振り返ろう
『子どもを呪う言葉・救う言葉』は、自身の子育ての方針や子育て観を振り返る意図で以下のような内容で構成されています。
- 子どもを犯罪者にすることになった「危ない一言」の事例
- 事例の何が問題だったのか
- 事例のような場合に親としてはどのようにするべきだったのか
『子どもを呪う言葉・救う言葉』で出てくる事例は、親がよかれと思って投げかけた言葉(よかれと思っていなくても親としては何気ない言葉)が呪いの言葉となって子どもを犯罪者にすることになったものばかりです。
子育てに正解はないと思います。
しかし、親である私自身も子どものためを思って投げかけている言葉があるのですが、それが『子どもを呪う言葉・救う言葉』で紹介されている「危ない一言」の中にありました。私は子育てを振り返る良いきっかけになりました。
以下では、『子どもを呪う言葉・救う言葉』で出てきた6つの「危ない一言」それぞれについて、私が大事だと思ったものを私の解釈も織り交ぜながらまとめます。
「みんなと仲良く」が個性を破壊する
自己決定する力が弱くなる
「みんなと仲良く」を言われ続けると、周囲の反応を伺いながら生活する子どもになり、自己決定する力が弱くなります。
子どもの興味を否定した
事例の親としては協調性が大事という価値観から「みんなと仲良く」という言葉を言っていました。この価値観は問題ありません。
しかし、子どもの興味・関心を否定することになってしまったため、「みんなと仲良く」という言葉が子どもにとって「個性を抑えろ」という意味になってしまいました。
短所=長所の言い換えをする
子どもが親の価値観と異なる行動をしている場合、短所として見てしまいがちです。
そこで、短所を長所として言い換えができるようになると、子育てが楽になります。例えば、子どもが後先考えずに行動することを親が短所として感じるのであれば、「普通だったらいろいろ考えてしまうようなことを即断即決できることは凄い」というように褒めるということです。
「早くしなさい」が先を読む力を破壊する
事前予見能力が弱くなる
「早くしなさい」と言われ、将来の夢や目標を持つことがなく、目の前のことをどうするかばかり考えると事前予見能力が乏しくなります。
事前予見能力とは、先を読む力のことです。
早くするべき理由を説明しなかった
親が子どもに早くするべき理由を説明しないと、子どもは発達の過程で事前予見能力が身につきません。
逆算して考える習慣づけと様々な体験をすること
事前予見能力を育てるためには、日常の中で目的から逆算して考えることをすると良いです。
例えば、旅行に行く予定があるなら、計画を考えるなどです。
そして、事前予見能力(先を読む力)には、単純な先読みだけでなく、想定と違った場合の対応もできるようにしておくことが大切です(多様な先読み)。
多様な先読みのためには、様々な体験をすることが大切です。体験をすることにも限界がありますから、本を読んで体験の事例を増やすことが重要になります。
「頑張りなさい」が意欲を破壊する
「頑張って」で意欲を持たせることはできない
「頑張って」は、普通は応援の意味で使われる言葉です。
しかし、子どもによっては自分を否定する言葉に聞こえます。意欲を破壊してしまいます。
親が自分のことを大事に思っていると子どもは感じなかった
日頃のコミュニケーションの中で、親が子どものことを大事に思っていると子どもに伝えていないと、ポジティブな言葉も否定的に受け止められるようになります。
意欲を持っていることを褒める
意欲(やる気)は自分の内側から出てくるもので、他者が植えつけることはできません。できることは、意欲を促すことができるだけです。
親としてできることは、小さくても子どもが意欲を持っていること自体を褒めると子どもの意欲が高まります。そして、プロセスも褒めるとますます意欲を引き出すことができます。
例えば、家事ができるようになりたいと思っていること(意欲)に対して褒める。そして、洗濯物が畳めていること(プロセス)に対しても褒めるということです。
「何度言ったらわかるの」が自己肯定感を破壊する
子どもに伝わっているという思い込みが子どもの自己肯定感を下げる
親が自分の子どもに対して他の家の子どもを褒めるという伝え方をすることで、親は自分の子どもに他の家の子どものようになって欲しいという思いがありました。親としてはこの伝え方は正しいと思っていたとしても、子どもに伝わらない場合があります。
むしろ、子どもとしては、親から自分自身が褒められないため、自己肯定感が下がり、自分が承認された感覚を持つために犯罪に走る場合があります。
子どもへの期待と思い通りにいかない子育てのストレスからキレてしまった
親の言いたいことが子どもに伝わっていなかったとしても、親はキレてはいけません。キレてしまうと、子どもの自己肯定感を下げる強いきっかけになるからです。
子どもが理解できる伝え方か、伝えようとしている内容が親の思い込みになっていないかを考える
何度言っても子どもがわかってくれないという場合、まず、子どもが理解できる伝え方をしているかを考える必要があります。何度も同じことを言わないといけないということは子どもが理解できない言い方をしているのだと考える必要があります。
そして、親として伝えたい内容が本当に子どものためになるものなのかを点検する必要があります。
「勉強しなさい」が信頼関係を破壊する
子どもを無視した言葉は子どもを失望させる
勉強ができて将来を期待されているいい子であっても、子どもを無視した言葉である場合、子どもの親への信頼を失わせて犯罪に走らせることがあります。
子どもの気持ちを無視して期待を伝えるばかりだったことと、子どもの努力を認めなかったこと
親が一方的に期待を伝えるばかりで、子どもと話し合おうとはしなかった。そして、子どもの努力を認めず、結果だけを見て子どもを非難しました。
この場合、子どもは大変なプレッシャーにさらされることになります。
子どもと信頼関係を築く
子どもが勉強しようと思っている時に「勉強しなさい」とは言わない。加えて、普段から子どもとよく話し合って信頼関係を築いておくことが大切です。特に、勉強以外の話題も持っておく方が、様々な話ができて子どもがリフレッシュできてやる気も湧いてきます。
「気をつけて!」が共感性を破壊する
共感能力が低くなる
「気をつけて!」と言って、過保護・過干渉になると共感能力が低くなります。
共感とは、人の感情を正確に認知できることと人の感情を正確に推測できることをいいます。
同年代の子どもたちと関わる体験を不足させていた
過保護・過干渉によって、同年代の友だちと遊ぶことを禁止してしまったため、共感能力が低くなってしまいました。
あえて失敗させる
まず身体生命の安全に関わるかどうかを判断し、それ以外はどこまで許容できるかを考えておく必要があります。本当に子どものためを思うのであれば、あえて失敗をさせて乗り越えさせることも大切です。
まとめ:子育ての方針を振り返ろう
出口保行(2022)『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』SBクリエイティブ株式会社を参考に子どもを犯罪を走らせることになった「危ない一言」を紹介しました。
「危ない一言」とは、
- 「みんなと仲良く」
- 「早くしなさい」
- 「頑張りなさい」
- 「何度言ったらわかるの」
- 「勉強しなさい」
- 「気をつけて!」
です。
「みんなと仲良く」を言ってはいけない理由は、自己決定する力が弱くなるからです。子どもの興味・関心を否定しないようにしましょう。子どもが親の価値観と異なる行動をしている場合は、長所に言い換えをしましょう。
「早くしなさい」を言ってはいけない理由は、事前予見応力が弱くなるからです。日常の中で目的から逆算して考える習慣づけと様々な体験をさせましょう。
「頑張りなさい」を言ってはいけない理由は、子どもによっては自分を否定する言葉に聞こえます。意欲を破壊してしまいます。子どもが小さくても意欲を持っていること自体を褒めましょう。そして、プロセスも褒めるようにしましょう。
「何度言ったらわかるの」を言ってはいけない理由は、子どもに伝わっているという思い込みが子どもの自己肯定感を下げるからです。子どもが理解できる伝え方をしているか考えましょう。そして、親として伝えたい内容が本当に子どものためになるものなのかを考えましょう。
「勉強しなさい」を言ってはいけない理由は、子どもを無視した言葉である場合、子どもの親への信頼を失わせるからです。子どもが勉強しようと思っている時に「勉強しなさい」とは言わない。普段から子どもとよく話し合って信頼関係を築いておきましょう。
「気をつけて!」を言ってはいけない理由は、過保護・過干渉になると共感能力が低くなるからです。身体生命の安全に関わるもの以外はあえて失敗させて乗り越えさせることも大切です。
以上、『子どもを呪う言葉・救う言葉』を読んで私なりにまとめてみました。
これらの内容を読んで少しでも気になった方は『子どもを呪う言葉・救う言葉』を読むことをお勧めします。事例と犯罪心理学者である出口保行氏の詳細な解説を読んで子育ての方針を振り返るきっかけにしてもらえればと思います。
育児を楽しんでいきましょう!